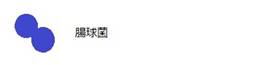獣医師会研究会
抗生物質の使用法2
|
グラム染色の方法 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ハッカーの変法 フェーバー法 バーミー法 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
ステップ1 塗抹、乾燥、固定 塗抹後、火炎固定(ドライヤーでも可)orメタノール固定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
ステップ2 グラム陽性菌の染色 ビクトリア青駅(染色液A)を注ぐ(20秒から1分) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
ステップ3 グラム陽性菌の媒染・分別 脱色液(数秒から30秒)後、水洗 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
ステップ4 グラム陰性菌の染色 染色液B(サフラニンorフクシン)を注ぐ。水洗、乾燥 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表的な細菌グループ(感染疾患の原因菌はそんなに多くない) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
グラム 陽性 球菌 |
A |
ブドウ球菌 |
Staphylococcus |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
B |
連鎖球菌 |
Streptococcus |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
C |
腸球菌 |
Enterococcus |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
グラム 陰性 桿菌 |
D |
大腸菌グループ |
E.coli、Klebsiella.pneumoniae、 Proteus.mirabilis(PEK) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
E |
緑膿菌グループ |
Serrati、Pseudomonas、Acinetobacter、 Citorobacter、Enterobacter (上記5つで:SPACE) |
感染力は弱い →免疫低下(クッシングなど)を考慮 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
F |
嫌気性菌グループ |
Bavteroides.fragilis |
腸の中の特殊な菌 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
腸球菌 |
連鎖球菌 |
ブドウ球菌 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
その他 |
緑膿菌は桿菌の中でも小さい方 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
グラム陽性桿菌 クロストリジウム、コリネバクテリウム、リステリア、バチルス |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
嫌気性菌はどこにいる? 猫の皮下膿瘍、膿胸、消化管穿孔時の腹膜炎 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
膀胱炎で多い菌 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
犬:グラム陰性81.4%・大腸菌58.1%、プロテウス7.0% グラム陽性18.6%・腸球菌9.3%、ブドウ球菌7.0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
猫:大腸菌37.3%、腸球菌28.6%、ブドウ球菌19.8%、プロテウス4.8% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
覚えておきたい抗菌薬 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
限定27種 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
βラクタム系抗菌薬 |
ペニシリンG、アンピシリン、アモキシシリン、アンピシリン・スルバクタム、 アモキシシリン・クラブラン酸、ピペラシリン・タゾバクタム、セファゾリン、 セフトリアキソン(またはセフォタキシム)、 セフェピム、イミペネム、メロペネム セフポドキシム(シンプリセフ)、 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
グラム陽性菌のカバー薬 |
バンコマイシン、リネゾリド |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
アミノグリコシド系抗菌薬 |
ゲンタマイシン、トブラマイシン、アミカシン |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ニューキノロン系抗菌薬 |
シプロフロキサシン、レボフロキサシン、モキシフロキサシン、エンロフロキサシン |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
マクロライド系抗菌薬 |
エリスロマイシン、クラリスロマイシン、アジスロマイシン |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
テトラサイクリン系抗菌薬 |
ドキシサイクリン、ミノマイシン |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
そのほかの抗菌薬 |
クリンダマイシン、ST合剤、メトロニダゾール |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
抗菌薬の投与方法 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
濃度依存性:アミノグリコシド、キノロン →最高血中濃度に抗菌作用が依存 →一回投与量を増やす 時間依存性:βラクタム →どのくらい長い時間、MICよりも高い濃度になるか →頻回投与が重要 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
殺菌的、静菌的 殺菌的で上表のβラクタムからキノロンまでとST合剤。残りは静菌的。 免疫抑制状態にある場合は殺菌的なものを選ぶ。 ただ、多くの場合であまり考慮しなくてもよい。 免疫力が極度に低下、敗血症、菌血症、感染性心内膜炎、重症感染症、好中球減少症では殺菌性が必要 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ペニシリン系 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
基本:グラム陽性球菌をカバー(ブドウ球菌、連鎖球菌、腸球菌) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
特に連鎖球菌と腸球菌:ペニシリンG 広域ペニシリン:グラム陽性+グラム陰性(大腸菌):アンピシリン(注射)、アモキシシリン(経口) 合剤(腸内細菌、嫌気性菌、ブドウ球菌):アモキシシリン・クラブラン酸(経口)、アンピシリン・スルバクタム(注射) クラブラン酸とスルバクタムはβラクタマーゼ阻害剤 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合剤の投与量 クラブラン酸は無視して、アモキシシリンの量で考える |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
グラム染色から選ぶ第一選択 グラム陽性球菌 1:腸球菌(連鎖球菌):アモキシシリン 2:ブドウ球菌:セファレキシン、アモキシシリン・クラブラン酸 グラム陰性桿菌 大腸菌:アモキシシリン・クラブラン酸、アモキシシリン |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
オーグメンチン :AMPC:CAV= 2:1 クラバモックス小児用配合シロップ:AMPC:CAV=14:1 CLAVAMOX(海外) :AMPC:CAV= 4:1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
経口:アモキシシリン・クラブラン酸カリウム(オーグメンチン) 静注:アンピシリン・スルバクタム(ユナシンS) 基本グラム陽性球菌をカバー+グラム陰性菌(腸内細菌)+嫌気性菌+ブドウ球菌 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
緑膿菌に効果的なペニシリン |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
ピペラシリン、ピララシリン・タゾバクタム(合剤) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
SPACE(緑膿菌グループ) Serrati Pseudomonas(緑膿菌) Acinetobacter Citorobacter Enterobacte これらの菌は日和見感染眼基本。基礎疾患がある症例の場合はこれらを想定。 →基礎疾患がある症例では培養するべき。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
緑膿菌に効果のある抗菌剤 ペニシリン系:ピペラシリン セフェム系:第3世代の一部(セフダジジム)、第4世代(セフェピム) ニューキノロン系:バイトリルなど カルバペネム系:イミペネムなど アミノグリコシド系:アミカシンなど |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
ピペラシリン・タゾバクタム 犬猫:文献上:50mg/kgIV、IM:4〜6時間毎 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ペニシリン系のイメージ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
グラム陽性菌に強い。好気性も嫌気性も(ブドウ球菌はダメ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ペニシリン系まとめ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
グラム陽性球菌 |
グラム陰性桿菌 |
嫌気性菌 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
連鎖球菌 |
肺炎球菌 |
ブドウ球菌 |
腸球菌 |
感受性良い |
中間 |
悪い |
横隔膜より上 |
横隔膜より下 Bacteroides Fragilis |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
MSS |
MRS |
E.faecalis |
E.facium |
大腸菌 Klebsiella Proteus |
Enterobacor Serratia Citorobactor |
緑膿菌 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ペニシリンG |
◎ |
◎ |
× |
× |
◎ |
× |
× |
× |
× |
○ |
× |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
アンピリン(アモキシシリン) |
◎ |
◎ |
× |
× |
◎ |
× |
△☆ |
× |
× |
○ |
× |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
アンピシリン・スルバクタム |
○ |
○ |
○ |
× |
○ |
× |
○ |
× |
× |
○ |
○ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ピペラシリン |
○ |
○ |
× |
× |
○ |
× |
○ |
△ |
○ |
○ |
△ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
◎:著効、○:有効、△:菌によっては効く、×:無効、☆:Klebsiellaは耐性 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
セフェム系 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
第一世代から第四世代まである。 グラム陽性球菌に始まり、グラム陰性桿菌に終わる |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
第一世代 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
セファゾリン(注射)、セファレキシン(経口) グラム陽性球菌、ブドウ球菌、連鎖球菌 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
グラム陽性球菌に作用 ペニシリナーゼに安定 →ブドウ球菌にも有効 耐性ブドウ球菌、腸球菌には効果がない PEK(グラム陰性菌)には有効 →術前投与、膿皮症に有効 →皮膚のブドウ球菌を抑えるため |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
最近のセファレキシンの乱用で、 メチシリン耐性ブドウ球菌が増加 山口県は半分、農工大では80%が耐性化 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
第二世代 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
セフメタゾール(注射) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
PEK+嫌気性菌(バクテロイデス属)に効果 下部腸管、生殖管の手術で予防的に使用(医学) ESBL産生菌にも効果ある? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
ESBL産生菌 基質拡張型β−ラクタマーゼ(ESBL)産生菌 →ようするに多剤耐性菌 ほとんどの抗菌剤に耐性 大腸菌、クレブシェラ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
伴侶動物から分離されたESBL産生大腸菌に感受性のある抗菌薬 ファロペネム、メロペネム、セフメタゾール、ホスホマイシン、アミカシン |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
犬:20〜22mg/kg、IV、8時間毎 猫:情報無し |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
第三世代 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
グラム陰性桿菌 特に腸内細菌(大腸菌、クレブシエラ)に極めて有効 院内感染で問題となるEnterobacterやCitrobacterなどの腸内細菌、Serratiaにも効果あり グラム陽性菌には活性弱い 下部消化管穿孔などで使用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
緑膿菌に作用なし、グラム陽性球菌に多少効果 セフォタキシム、セフトリアキソン 緑膿菌に作用あり、グラム陽性菌に効果無し セフタジジム |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
セフォタキシム 犬:50mg/kg、12時間毎、IV、IM、SC 文献では、敗血症で20〜80mg/kg、IV、6〜8時間毎との記載あり 猫:20〜80mg/kg、6〜8時間毎、IV、IM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
セフトリアキソン 犬:25mg/kg、IV、IM、12〜24時間毎 猫:25〜50mg/kg、IV、IM、12時間毎 人では、1日1回でいい第3世代セフェム 犬でも、50mg/kg、IMなら24時間毎でOKとの記載もあるが、25mg/kg、IVで24時間毎でいいのかわかりません 25mg/kg、IVなら12時間毎が無難かもしれません |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
セフタジジム 犬:30mg/kg、6〜8時間毎、IV 猫:25〜30mg/kg、8時間毎、IV 成書にはIMも可能と記載 緑膿菌感染で重症、キノロンが効かないときに使用 猫での使用経験はなし 副作用はあまり報告無し |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
第四世代 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
セフェピム 第一世代+第三世代みたいな感じ グラム陰性菌、陽性菌の多くをカバー 緑膿菌もカバー 人では、重症院内肺炎、敗血症、好中球減少者の発熱などに使用 カルバペネム系と同様に簡単に使用してはいけない 嫌気性菌には弱い |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
犬:40mg/kg、IV、6時間毎 1日4回投与するので大変 猫での報告は無し |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
セフェム系の抗菌薬は最初は生食など希釈して30分以上かけて点滴している 問題が無ければ、ワンショットで投与も可能だと人では報告あり。セフェム系以外はワンショットでIVは不可な事が多い。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
セフェム系はどの世代も腸球菌には効果なし →ペニシリンが有効 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
グラム陽性球菌 |
グラム陰性桿菌 |
嫌気性菌 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
連鎖球菌 |
肺炎球菌 |
ブドウ球菌 |
腸球菌 |
感受性良い |
中間 |
悪い |
横隔膜より上 |
横隔膜より下 Bacteroides Fragilis |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
MSS |
MRS |
E.faecalis |
E.facium |
大腸菌 Klebsiella Proteus |
Enterobacor Serratia Citorobactor |
緑膿菌 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
第一世代 セファゾリン |
○ |
◎ |
◎ |
× |
× |
× |
○ |
× |
× |
○ |
× |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
第二世代 セフメタゾール |
◎ |
◎ |
◎ |
× |
× |
× |
○ |
○ |
× |
○ |
○ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
第三世代 セフォタキシム |
○ |
○ |
◎ |
× |
× |
× |
○ |
○ |
× |
○ |
× |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
第四世代 セフェピム |
○ |
○ |
○ |
× |
× |
× |
○ |
○ |
○ |
× |
× |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
セフメタゾール:単剤でPECや嫌気性菌をカバー。消化管手術の予防的投与 セフォタキシム:消化管穿孔などで使用。嫌気性菌のバクテロイデスがカバーできないので、クリンダマイシンかメトロニダゾールをを併用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
経口第三セフェムは? セフポドキシム:吸収率は悪い:シンプリセフ 1日一回の投与であるため、飼い主さんの投薬回数が軽減されます。 有効菌種、本剤感受性のブドウ球菌属、連鎖球菌属、大腸菌、プロテウス、ミラビリス 適応症:犬・細菌性膿皮症 第二選択薬として使用。セファレキシンに効果のないブドウ球菌に使用?効かない? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
コンベニアは? 第三世代セフェム 注射で2週間効果。 ブドウ球菌、大腸菌には効果あり →腸球菌には効果少ない(効果あるかもしれないが、なるべく初診時には処方しない) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
コンベニアの感受性は? 外注検査:株式会社ランス モノリス、サンリツセルコバ検査センター、その他? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
カルバペネム系 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
イミペネム、メロペネムなど 医学では使用を制限。 第四世代セフェム系+嫌気性菌のイメージ 最終兵器、人では、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌が問題(CRE:Carbapenem-resistantEnterobacteriaceae) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
イミペネム・シラスタチン シラスタチン:イミペネムが腎臓で分解されるのを防ぎ、イミペネムの腎障害の軽減をする メロペネム イミペネムより発作の副作用が少ない? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
イメージ:何でもかんでも重点爆撃 →ほとんど細菌に効く →効かない菌を覚える 効かない菌:腸球菌、耐性ブドウ球菌(MRS) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ファロペネムは・・・ ペネム系抗菌薬 グラム陽性球菌に有効→βラクタマーゼに安定な古典的ペニシリン →カルバペネム系ではない |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
犬猫の投与量は確立されていない 犬猫:5mg/kg、TIDで治療可能と報告あり 子犬に様々な量のフェロペネムを投与し、かなりの高用量でも副作用が認められないとの報告あり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
経口カルバペネムは? オラペネム 世界初の経口カルバペネム系抗菌薬 本来カルバペネムは重症患者用 外来で治療できるなら必要ない |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
バンコマイシン |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
グラム陽性菌の最終兵器 →グラム陽性菌なら何でも効果あり MRSA感染症の特効薬の一つ 最初から使用しない |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
人での使用 急速に静脈注射:ヒスタミンが遊離:首から上が赤くなるレッドネック症候群 →血圧低下 一時間かけてゆっくりと点滴静注 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
バンコマイシンの経口 消化管吸収されない 一般的な治療には使用できない 骨髄移植時の消化管殺菌や感染性腸炎の治療(消化管内の菌を殺す) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
キノロン |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
人では第一世代〜第四世代 第1世代:グラム陰性菌PEK 第2世代:第1世代+緑膿菌 第3世代:第2世代+グラム陽性球菌(連鎖球菌など) 第4世代:第3世代+嫌気性菌 →ニューキノロン、フルオロキノロン |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
エンロフロキサシンは? グラム陰性菌に効果 陽性菌もカバー(腸球菌の効果は限定的) →アモキシシリン、セファレキシンで 人では耐性菌が増加している(動物?) 第2選択薬 緑膿菌に効果 副作用の問題 大腸菌の第二選択薬、緑膿菌感染の膀胱炎に |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
キノロンのイメージ グラム陰性桿菌と少しの陽性球菌(アミノグリコシドに類似) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
グラム陽性球菌 |
グラム陰性桿菌 |
嫌気性菌 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
連鎖球菌 |
肺炎球菌 |
ブドウ球菌 |
腸球菌 |
感受性良い |
中間 |
悪い |
横隔膜より上 |
横隔膜より下 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MSS |
MRS |
E.faecalis |
E.facium |
大腸菌 Klebsiella Proteus |
Enterobactor Serratia Citorobactor |
緑膿菌 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ニューキノロン |
○ |
◎ |
○ |
× |
? |
× |
○ |
○ |
○ |
× |
× |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
第三世代セフェム |
○ |
○ |
◎ |
× |
× |
× |
○ |
○ |
× |
○ |
× |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
クリンダマイシン |
○ |
○ |
○ |
|
|
|
|
|
|
○ |
○ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ST |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
|
|
◎ |
◎ |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
クリンダマイシン |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
グラム陽性菌と嫌気性菌をカバー 口腔内細菌は、グラム陽性菌と嫌気性菌が多いので皮下膿瘍にも適用可能 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
嫌気性菌に効く静注抗菌薬:特にBacteroides セフメタゾール、フロモキセフ、クリンダマイシン、アンピシリン・スルバクタム、タゾバクタム・ピペラシリン、 セフォペラゾン・スルバクタム、メトロニダゾール、カルバペネム系 消化管穿孔で他の抗菌薬と併用するなら、クリンダマイシンかメトロニダゾール |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
嫌気性菌+グラム陽性菌 点滴用があり |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
メトロニダゾール |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
グラム陽性菌、陰性菌には効かない 横隔膜下の嫌気性菌(バクテロイデス・フラジリス、クロストリジウム・ディフィシル) 寄生虫 慢性腸症にも使用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ST合剤:トリメトプリム・スルファメトキサゾール |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
細菌の葉酸代謝の酵素を阻害 2カ所別々の箇所で阻害→相乗効果 発展途上国では安価な広域抗菌薬として使用 前立腺によく移行 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
スルファジアジン+トリメトプリム:動物用のみ スルファメトキサゾール+トリメトプリム:人体薬 有効性の違いは報告無し |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ホスホマイシン |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
グラム陰性菌、グラム陽性菌に幅広く感受性 尿路感染症に使用? ESBL産生菌にも? 古くて新しい |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
犬:40mg/kg〜80mg/kg、PO、1日2〜3回 演者は、40〜50mg/kgで使用している。今の所、尿路感染症でのみ使用。 経口での吸収が悪い。副作用で消化管障害あり。 人の投与量より多いので人を参考にしない 腎障害にも注意する |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
猫は腎毒性があるため使用しない 20mg/kgでも腎障害の報告あり |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ブドウ球菌 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
動物(特に犬の皮膚) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
メチシリン感受性:第1世代セフェム(セファレキシン) メチシリン耐性 :ドキシサイクリン、ミノマイシン |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
連鎖球菌 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
犬では、StreptococcusCanis 皮膚感染症などでよく見る(咽頭、皮膚などに存在) ペニシリン系は十分効果あり(というより、ペニシリン系が一番) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
腸球菌 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
腸内にいるグラム陽性菌(弱毒株) 自然耐性が強い エンピリックなEnterococcusのカバーは市中腹腔内感染症では必要ない 複合感染時のEnterococcusは治療しないでOK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
セフェム系は1st〜4th全て無効 ニューキノロン系は感受性でも、UTI以外は効果なし IPM/CSでも、他のカルバペネムは効果弱い E.faecalisの第1選択はペニシリン系、E.faeciumの第1選択はバンコマイシン |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PEK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
E.coli、Klebsiella.pneumoniae、Proteus.mirabilis |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
腸内細菌(膀胱炎、子宮蓄膿症、腹腔内感染症の原因) 耐性が無ければ何でも十分効果あり:アモキシシリン、C/AMPC、第一世代セフェム系、キノロン、ST |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
どのくらい耐性菌が出ているかも問題 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
まとめ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ブドウ球菌:セファレキシン 連鎖球菌 :セファレキシン、アモキシシリン 腸球菌 :アモキシシリン |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
大腸菌グループ:アモキシシリンクラブラン酸、キノロン、ST合剤、第三世代セフェム 緑膿菌グループ:キノロン、第三世代セフェムの一部、第四世代セフェム、カルバペネム 嫌気性菌グループ:クリンダマイシン、メトロニダゾール、アモキシシリン |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
血液培養 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
血液培養ボトル |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
好気用レズンボトル:採血量:3〜10ml、適切な採血量:8〜10ml 偏性好気性菌、通性嫌気性菌、真菌などの分離培養 嫌気性用レズンボトル:採血量:3〜10ml、適切な採血量:8〜10ml 偏性嫌気性菌、通気性嫌気性菌などの分離培養 小児用レズンボトル:適切な採血量1〜3ml |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
サンリツセルコバ検査センター 血液培養ボトルVersaTREK-TM-Redoxを使用 血液は0.1〜1mlで大丈夫だとのこと |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
大阪にもあり ベッツクリニカルラボ 0.1mlから血液培養可能 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
血液培養の方法 1:毛刈り 2:消毒して採血 3:採取後、針を変えずに、嫌気ボトル→好気ボトルへ 4:転倒混和 嫌気ボトルには空気を入れない 出来れば2セット作成する 室温で検査センターへ輸送 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||