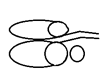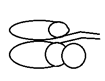�ׁ[�����K�[�Z�~�i�[
���������Z�~�i�[�Q�O�P�T
|
���̑m�X�ٕ��s�S�ǂɑ��������x�������ǂ̐f�f |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
�����@�����猩���������̔x�������ǂ̕��� |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
�x������������ �@�����𒎏ǁA��V���S�g�x�z�Z����V���S�����A�������A�����lj������� ���S�s�S�Ɋ֘A����x������ �@�m�X�ٕ��s�S�ǁA�S�؎����A���̑��̍��S�n���� �x�����܂��͒�_�f�� �@�����ǐ��x�����A�Ԏ����x���ۏǁA��ᇁA���ܓx�A�������x�������ǎ��k�i�x����ɂ���_�f�ǁj �����ǁE�ǐ��ǂɂ��x������ �@�ǐ��� �@�@�Ɖu��ݐ��n�����n���A��ᇁA�S�����A�`���R�o�������i�t�ǁA���ǁj�A���t�玿�@�\���i�ǁA �@�@�d�퐫���Ǔ��ÌŁA�s���ǁA�O���A�ŋ߂̎�p �@���� ���̑� �@�������}�X�a�ρi��ᇁA�����j |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
�x�������ǂ̊�b�����̔�r �@�ȑO�̓t�B�����A�ǂ��������������݂͑m�X�ٕ��s�S�ǂ��ł����� �@���m�X�ق��S�t�ϐ��@���ق̔�����@�����S�[�����̏㏸�@���x�Ö����̏㏸ �@�@�@���x����@�������@���x�������̏㏸�@���E�S�����̏㏸�@���O��ًt���@�� |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
�m�X�ٕ��s�S�ǂł́A�X�e�[�W���i�s����ɂ�āA�x�������ǂ̗L�a�����㏸����B �@�A�C�U�b�N�P���F�T���ȉ��A�P���F�P�R���A�Q�F�Q�T���A�R�F�V�O���@�@�@���A�C�U�b�N�̕��� �@�@���X�e�[�W���i�s����قǁA���[�����㏸���� �@�@���ߋ��ɔ�ׂāA����ȂǂŐ������������A�X�e�[�W�i�s��������Ă��� |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
�V�O�i�������g �@�d�x�̍��S�s�S�A�V��A���i�l�q�͗Y�ɑ����@�����̕����S�؍זE�����Ȃ�����H�j �@���^���A�e���A��i�����ے肳��邩������Ȃ��j �@�@�����[�����㏸���₷������@���x���������N�����₷�� |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
�Տ��Ǐ� �@���S�s�S����F�^���s�ϐ��A����A�p�ċz�A�ċz����A���P�i����j �@�E�S�s�S����F�����A�S�����i�����j�A�̎��@�����ŋ��������܂邱�Ƃ͒����� �@���S�s�S����F���_�@�����_������A�x�����������邱�Ƃ����� |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
�S�����̎��_�ƂĂ�̊ӕʃ|�C���g �@�@�@�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�S�����@�@�@�Ă� �@�����̉@�@�@�@�@�@�@�����@�@�@�@�x�� �@�����̋��A�����~�@�@�Ȃ��@�@�@�@���� �@����̃^�C�v�@�@�@�@�@�@�@�o�ɐ��@�@�@�d���� �@�쎞�̕s�����@�@�@�@�@����@�@�@�@�Ȃ� |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
�S�����u�̔�r |
|
���S���o���~�` |
|
���S���o���G���� ���u���E�S���ɉ�����āA ���S�o���G�������� ���S�o�������@�����_���� |
||||||||||||||||||||||
|
|
�S���̒��f �@�m�X�ًt���F�m�X�ٌ����i�������ǁj�ōő�A���k���t���� �@�O��ًt���F�O��ٌ����i�E�����ǁj�ōő�A���k���t�����@�@�@�����O��ًt���̕������� �@�x�����ًt���F�x�����ٌ����i�������ǁj�ōő�A�g�����@�@���x�����ًt���̎G����G�R�[�Ŕx�����t�������邱�Ƃ͏��Ȃ� �����E�����̎G��������ꍇ�A�������łǂ���̎G�����͔��ʏo���Ȃ� ���E����G�����������Ă�����A�x������������ƍl���� �@���o�C���Q�F�T�T���A�R�F�U�W���A�S�F�V�W���A�T�F�W�R���A�U�F�X�O���@���x�������̗� |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
�m��f�f�͐S�G�R�[�}���� �@�h�v���@�F�O��ًt�����������Q�D�T�`�R���^�������@�@�@�����k���x�������f �@�@�@�@�@�@�x�����ًt�����@���Q�`�Q�D�T���^�������@�@�@���g�����x�������f �@���O��Ƃ��āA�x�����ً����݂��Ȃ��A�x�������ǂȂ�K���ǂ��炩�̋t�����o�� ������ł́A���m�ɋC�y�Ƀh�v�����o���Ȃ���E�E�E |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
�����w�� �@�O�t�ƌ�t�̔x�����Ɣx�Ö��̑����ōl���� |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
�S���G�R�[ |
|
�E���ǂ���̍������o�H�n ��ԉE�����x���� |
|
�x�������g�����A ���S�[�������ό`�����Ă��� |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
�P�ɍ��[���傫�������ł́A�x�������ǂƌ����Ȃ� |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
�S�G�R�[�}������p���Ȃ��A�x�������\�����f���� �@�X�R�A���R�D�P�Q�X�i�r�|�������T�D�Q���̗L���j�{�Q�D�V�R�O�i�����ڐG�����R�D�R���̗L���j�|�T�D�R�W�X �@�o�f���P�^�i�P�{�������i�|�P�~�X�R�A�j�j �@�o�f���O�D�T�Ȃ�x����������Ɣ��f �@���x�F�\���m���W�T�D�X���A�z���I�����F�W�V�D�T���A�A���I�����W�T�D�T�� �@�Տ�����ł̊��p�@�F�r�|�������T�D�Q���������ڐG�����R�D�R�� �@�@����W�U���̊m���Ŕx������ �@�r�|�������S���̒Z���A��S���ł̌������ |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
�x�������ǁF�b�莡�Ãv���g�R�[���F���b��z��ȂQ�O�P�T �@�K���F�x�������Ɋ֘A����������Ǘ�B�Ȃ��Ă����Â�������]���邲�Ƒ� �@�@�@�@���Ǐ�F���_�������̂ǂ��炩������������� �@�P�F���S�s�S�̎��Â������@�@�����[���������邱�Ƃ����̖ړI�@���`�b�d�j�Q��������������g���܂��g�p �@�@�@�lj��E���ʁF���NJg����E���S�܁E���A�� �@�Q�F�s���x���^�� |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
�����I�ȑm�X�ًt�����f�����ł̃G�r�f���X �@�A�����W�s���F�O�D�Q�����^�����A�a�h�c �@�@�����x�i�[�v�����F�O�D�T�����^�����A�a�h�c �@�@�A�����W�s�����^�ɂ�荶�[�����L�ӂɒቺ�A�x�i�[�v�����ł͗L�ӂɒቺ���� �@�s���x���^�� �O�D�Q�T�����O�D�T�����^�����A�a�h�c�Ŕ�r �O�D�Q�T�����^�����ł����[���͗L�ӂɒቺ�A�O�D�T�����^�����ł�茰���ɍ��[�����ቺ |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
��L�ł��}�����Ȃ��ꍇ�́A�x�����g���܂�lj� �@���`�b�d�j�Q�܂ƃs���x���^�����ʂŎ��_�A�������}�����Ȃ��ꍇ |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
�x�������㏸������������ƁA�T�C�g�J�C���������������̕��ʂɉ��ǂ������� �@���x�����ǂ���������o�������Ȃ�@�������Ȃ�ƍ��[���������Ă��x�������͉�����Ȃ� |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
�e��x���������Ö�̖�p�ʂ���щ��i�̔�r |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
��ʖ� �i���i���j |
�ܗL�ʁ^�� |
���i�i�~�j�^�� |
�����P��� ����� |
5kg�̌��ł� 1���i�j�~�j |
���̑� |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
��۽�����ݐ��� �i�x���i�[���j |
�Q�O���� |
�Q�X�D�X�~ �i�P�P�O�~�j |
2-5ug/kg BID-TID |
�R�O�|�P�P�Q�~ �i110-413�~�j |
�����������܂�����Ȃ� |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
�{�Z���^�� �i�g���N���A�j |
62.5mg |
4370.1�~ |
2-5mg/kg BID |
1398-3496�~ |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
�V���f�i�t�B�� �i�o�C�A�O���j |
�Q�T���� |
�X�P�T�~ �i2100�~�j |
1-2mg/kg SID-BID |
183-1098�~ �i420-2520�~�j |
���_�A�����̉��P�ɂ͂��� 1mg/kgBID��7�� ���P�T�ŏǏ�̉��P������ �����i�ƏǏ���r���Čp���l�� |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
�V���f�i�t�B�� �i�o�C�A�O���j |
�Q�O���� |
1179.8�~ |
1-2mg/kg SID-BID |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
�^�_���t�B�� �i�V�A���X�j |
|
|
1mg/kg SID-EOD |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
�C�}�`�j�u �i�O���y�b�O�j |
�P�O�O���� |
2749.0�~ �i4790�~�j |
3mg/kg SID |
�S�P�Q�~ SID |
�C�}�`�j�u�́A �x�����̃����f�����O���N���� |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
���i���������̉��i�͓��b���i ��L�̖�܂ł��A�x�����������Ȃ������̂����ǂ��͓̂���@������ŕ����Ȃǂ͉��P���� |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
�V���f�i�t�B���A�ߋ��̎g�p�Ɠ��b��ł̌��� �P�D�X�i�O�D�T�|�Q�D�V�j�����^�����@�@�@�r�h�c�|�s�h�c�@�R�O��@�a��������A�Q�O�O�U �@�R�P�D�R�i�Q�D�O�W�|�T�D�T�U�����^�����j�@�r�h�c�|�s�h�c�@�Q�Q��@�j������������A�Q�O�O�V �@�@�P�����^�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�r�h�c�|�a�h�c�@�@�P��@�s������������������A�Q�O�O�V �@�O�D�T�|�P�D�O�����^�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�a�h�c�@�@�@�@�@�@�H�@�@���b�A�Q�O�P�R |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
�x���������ɑ����p�ʃC�}�`�j�u�̎��Ì��� �@���R���ǐ��x���������U���ɃC�}�`�j�u�𓊗^�F�R�����^�����A�r�h�c�A�R�O�� �@�@���^�O�Ɠ��^�R�O����̕ω��̕]�� �@�Տ����� �@�@���P����ё����X�R�A�͗L�ӂɉ��P�A�^���s�ϐ��A���_�A�����A������e�X�R�A�͕s�� �@������k���x�������͗L�ӂɒቺ�F���^�O63.3�}24.9�iSD�j�A���^��36.1�}1438mmHg ���x�������͉����邪�A���_�A�����̉��P�͓�� |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
�s���x���^���͗p�ʈˑ����ɁA�x�������A�x���ǒ�R��ቺ������ |
|||||||||||||||||||||||||
|
�L�̖����t���c�Q�O�P�T�A���j���E�A���W�I�e���V���n�}���܂�p�����V���Ȏ��Î�i |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
��Q�ɉ��������Ð헪���\�z���� �@�A��d�ቺ�@���\���ȋ��� �@���������ǁ@���H���Ö@�A�����z���� �@�����f���ǁ@���H���Ö@ �@�������@�@�@���q�`�r�}���܂Ȃ� �@�`���A�@�@�@���q�`�r�}���܁{�H���Ö@ |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
�������A�������A�`���A�͐t�s�S�̈����v�� |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
�a�t�m���㏸���錴�� �@�t�@�\��Q �@�E�� �@���`���H �@�㕔�����Ǐo���i���o���o���A�@�o���Ȃǂ��܂ށj �@�H��@�@���ʏ�ŐH��Q�`�U���Ԃ́A�a�t�m�͂R�O�`�S�O���㏸���� |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
�����̂ɖ�肪������@���`���A�{�@�����a�t�m�ɂȂ�@�������Ŏ��Â��J���Ă��x�� �`���A�@���t���`���A�@���ې��N�����̒`���A�ł͂Ȃ� |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
�b�����łb�j�c�̔L�̗\��͑�܂��ɗ\�z�ł��� |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
�h�q�h�r�X�e�[�W�FCre�l |
�������ԁE�N�i�����j |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
�a�������� |
�r�������� |
�j�������� |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
�P�F���P�D�U |
�m�` |
�O�D�X�V�i�R�T�V�j �P�i�R�U�T�j�a�o |
�m�` |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
�Q���F�P�D�U�|�Q�D�W |
�R�D�P�i�P�P�T�P�j |
�P�D�S�i�T�O�S�j �O�D�T�P�i�P�W�V�j�a�o |
�m�` |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
�R�F�Q�D�X�|�T�D�O |
�P�D�X�i�U�V�X�j |
�O�D�S�Q�i�P�T�S�j �O�D�V�V�i�Q�W�P�j�a�o |
�P�D�R�i�S�V�T�j |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
�S�F���T�D�O |
�O�D�P�i�R�T�j |
�O�D�P�U�i�T�V�j �O�D�O�T�i�Q�P�j�a�o |
�O�D�P�U�i�U�O�j |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
�a�o�F�����������L�A�m�`�F�]�������A�Q���F�����N���A�`�j���Z�x2.26-2.82mg/dl |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
�b��t���a�w�̒�� �@�O�D�S�����^���������錌���b�����Z�x�̑����͒P�Ȃ�덷�A�����ϓ��ł͂Ȃ� |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
�b�j�c�ł̌����j�Z�x�ُ̈� |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
��j���ǁF���A���ɏo���A�H�~�s�U�̌��ʐ����H�~�s�U�̌����ƂȂ�@���j��Y�������H���ɂ��� ���j���ǁF�R�`���A���ɏo���A��Ӑ��A�V�h�[�V�X�𐏔� |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
���� |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
�y�g���X�iPettrust�j�A�������l�`�o�͂��܂肤�܂�����o���Ȃ��ꍇ������ �t�N�_�l�d�̌����v�͔�r�I���肵�₷�� |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
�����܂��͏�� |
���i���j |
�L�i���j |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
�����t���a |
�X�|�X�R |
�P�X�|�S�U |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
�}���t���a |
�W�V |
�m�c |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
���t�玿�@�\���i�� |
�V�R�|�W�O |
�m�c |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
���A�a |
�Q�S�|�S�U |
�O |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
�얞 |
�e���킸�� |
�܂� |
�얞�͍������ǂɂȂ�ɂ��� ���L�͉����̎�肷���Ō������オ��ɂ��� |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
�������A���h�X�e������ |
�H�Ȏ��� |
�T�O�|�P�O�O |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
���F�זE�� |
�S�R�|�W�U |
�P�O�O�O�� |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
�b��B�@�\�ቺ�� |
�܂� |
�m�c |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
�b��B�@�\���i�� |
�m�c |
�Q�R�|�W�V |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
��������́A���ꓮ���ł�������ɂ�肩�Ȃ�Ⴄ �@����E���Ƒ��F�P�U�O�|�P�U�T �@�a�@�E���Ƒ��F�P�V�V�|�P�X�Q �@�a�@�E�b��t�F�Q�O�U�|�Q�P�T ���������������玡�Âł͂Ȃ��@���ꎞ�I�Ȃ��̂Ȃ���Ȃ��@���������������č������Ƃ���� |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
�`�b�u�h�l�K�C�h���C���ɂ��S�g���������̎��Ð��� �@��������E�W�I�튯��Q�i�s�n�c�j����э����ǂ̓��� �@�@���������P�T�O�^�X�T�����g���@���s�n�c�̍ŏ����X�N�A�R�`�U�����ȓ��ɍĕ]�� �@�@�@�������P�T�O�^�X�T�����g�� �@�@�@�@����^�����_�o�̂s�n�c����@���R�������Ö@�̊J�n�A�܂��͋����̓K�� �@�@�@�@�@��^�����_�o�̂s�n�c�Ȃ��@���V���ȓ��Ɍ����đ��� �@�@�@�@�@�@���������P�T�O�^�X�T�����g���@���P�`�R�����ȓ��Ɍ����ĕ]�� �@�@�@�@�@�@�@�����F�P�T�O�|�P�T�X�^�X�T�|�X�X�����g���@���s�n�c�̏؋������邩�H �@�@�@�@�@�@�@�@���x�����@���������Ö@�̊J�n�A�܂��͋�����K�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�m���@�@�����������̌������Ǘ��A�P�`�R�����ȓ��Ɍ����đ��� �@�@�@�@�@�@�@�����F�P�U�O�|�P�V�X�^�P�O�O�|�P�P�X�����g���@���s�n�c�̏؋��܂��͓��������̗v�������邩�H �@�@�@�@�@�@�@�@���x�����@���������Ö@�̊J�n�A�܂��͋�����K�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�m���@�@���Տ����f�F�������Ö@�̓K�p�܂��͂P�����ȓ��Ɍ����đ��� �@�@�@�@�@�@�@�������P�W�O�^�P�Q�O�����g�� �@�@�@�@�@�@�@�@�������Ö@�̊J�n�܂��͋�����K�� |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
�s�n�c�FTargetOrganDysfunction�A�W�I�튯��Q�A�����튯��Q �@�ዅ�F�e��Ԗ��a�ρA�o�� �@�S���F���S����� �@�t���F�i�s���t�@�\�ቺ�A�`���A |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
�h�q�h�r�F�S�g���������̎��ÊǗ� �@�P�F�H�����̂m���̐����@���������ቺ����Ƃ����G�r�f���X�͖��� �@�Q�F�W���I�ȗp�ʂł`�b�d�j�Q�� �@�R�F�`�b�d�j�Q�܂̗p�ʂ��Q�{�i�P���Q��j�� �@�S�F�`�b�d�j�Q�܁A�J���V�E���`�����l���u���b�J�[���p�Ö@ �@�T�F�`�b�d�j�Q�܁A�J���V�E���`�����l���u���b�J�[�A�q�h�����W�����p�Ö@ |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
�A��d |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
�A��d�̕��� �@�ᒣ�A�@�@�@�@�@�P�D�O�O�P�|�P�D�O�O�V�@���������ᒣ�@�@�@�������A�A�A���ǁA�����������ǁA���t�玿�@�\���i�� �@�����A�@�@�@�@�@�P�D�O�O�W�|�P�D�O�P�Q�@�����Ɠ����Z�x�̔A �@�s���S�ȔZ�k�A�@�P�D�O�P�R�|�P�D�O�Q�X�i���j�@�͂��ȔZ�k�A�@���n�����A�A�������A�̌���������Ɋ܂܂�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�P�D�O�P�R�|�P�D�O�R�S�i�L�j �@�����A�@�@�@�@�@�����P�D�O�R�O�@�@�@�@�@���������Z���Z�x�@���������A�͖��炩�ɔے�o���� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�L���P�D�O�R�T |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
�A��d���������h�ߗʂł͂Ȃ� �@���Z���A�����邩�ǂ����@�������A�����Ƃ��ɍ����A������Ă��邩�H�@�@�������A���ɑ��肷�� |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
�q�g�p�̋��܌n�ł́A���L�̔A��d�͐���������o���Ȃ� |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
�A�`���^�N���A�`�j����F�t�o�b |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
�A�`���Z�x�i�����^�����j�^�A�b�����Z�x�i�����^�����j �`���r���ʂ̎w�W �A��d�ɉe������Ȃ� �t�o�b�̉��߁i�l�R�j �@�����f���ǂȂ��F�t�o�b���O�D�S�`�P�D�O�F���Ӑ[�����j�^�[�i�����ǂ̕]���j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�t�o�b���P�D�O�F���������E���ÊJ�n�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���`�q�a�܂Ɛt���p�Ö@�H �@�����f���ǂ���F�t�o�b���O�D�Q�`�O�D�S�F���Ӑ[�����j�^�[�i�����ǂ̕]���j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�t�o�b���O�D�S�F���������E���ÊJ�n�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���`�q�a�܂Ɛt���p�Ö@�H |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
�C�k�l�R�̂t�o�b�̉��߂Ɋւ���K�C�h���C�� |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
�C�k �@�t�o�b�@���O�D�Q�@�@�@�@�@�`���A�͉A�� �@�@�@�@�@���O�D�Q�`�O�D�S�@���E��̒`���A �@�@�@�@�@���O�D�T�@�@�@�@�@�����`���A |
�l�R �@�t�o�b�@���O�D�Q�@�@�@�@�@�`���A�͉A�� �@�@�@�@�@���O�D�Q�`�O�D�R�@���E��̒`���A �@�@�@�@�@���O�D�S�@�@�@�@�@�����`���A |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
�C�k�l�R�Ƃ��ɔA�X�e�B�b�N�Œ`���A���z���A���ł��A�t�o�b���z���A���Ƃ͌���Ȃ� �@���A�X�e�B�b�N�̔A�`���͂t�o�b���Ă͂߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ� |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
�����̐��i�t���j�`���A�̗L�Q��p |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
�`���̑r���@�@�F��A���u�~�����ǁA�Պ������A����A�����A�o���X�� �t�Ԏ��g�D�j��F�t�@�\�ቺ�A�������ԒZ�k |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
�����̐��i�t���j�`���A�͐t����j�� �@�`���A�@���t���ʼn��ǂ�������@���t�Ԏ�����t�s�S���i�s���� |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
�t�o�b�ʂɌ��������t���a�̃l�R�̐����Ȑ� �@�����f���ǂ������Ă��Ȃ��Ă��A�t�o�b���O�D�S�Ƃt�o�b�O�D�Q�|�O�D�S�́A�t�o�b���O�D�Q���L�ӂɐ������Z�k �@���t�o�b���A�O�D�Q�ȏ゠��Ύ��Â��s������������ |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
�t���`���A�ɑ��鎡�Ð��� �@�t���a�p�Ö@�H�F�`���ܗL�ʐ����H�A�����f���ǂ��y���A�����̍��������ɘa �@���j���A���W�I�e���V���n�}���܁F�����̍��������ɘa�i�t�o�b��ቺ������j�A�~����p �@�����Ö@�i�����{�ɂ͊m��f�f�A�t�������K�v�j�@���X�e���C�h�܂͑��I���ł͂Ȃ��I �@�@���X�e���C�h�@�������㏸�@���t�o�b�㏸���� |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
�����t���a�̐i�s�Ɋ֘A����f�f���̊e��ϐ��̑��ϗʉ�͌��ʁi�l�R�j �@�ϐ��@�@�@�@�@�P�ʁ@�@�@�@�I�b�Y��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���l �@���������Z�x�@�����^�����@�P�D�P�S�i�P�D�O�W�|�P�D�W�S�j�@�O�D�O�P�Q �@�t�o�b�@�@�@�@�~�P�O�@�@�@�P�D�Q�S�i�P�D�O�U�|�P�D�S�T�j�@�O�D�O�O�W �����������Z�x���P�����^�����㏸���邩�A�t�o�b���O�D�P�㏸�����ꍇ�A �����t���a�̐i�s���X�N�͂��ꂼ��A�S�P���A�Q�S���㏸���� |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
�f�e�q�i�������h�ߗʁj�Ƃr�m�f�e�q�i�P��l�t�����������h�ߗʁj����݂��b�g�c�̐i�s�v���Z�X |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
�t�@�\ |
���� |
�y�x�`�����x�ቺ |
�d�x�ቺ |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
�l�t�������� |
���� |
�y�x�`�����x���� |
�d�x�ቺ |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
�f�e�q |
���� |
����`�o�x�ቺ |
�����x�`�d�x�ቺ |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
�r�m�f�e�q |
���� |
�㏸ |
�㏸ |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
���� |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
�Z�~���g���𖡕��ɂ��邽�߂� |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
�q�`�r�}����̓K���ǂ��H�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���K���ǂłȂ���Ύg�p���Ȃ� �@�S�g���������F�����̑���Ƃs�n�c�̗L�� �@�t�o�b�̏㏸�F�A������ϋɓI�Ɏ��{�A�������@�͐M���o���Ȃ� ���a��Ԃ͐��킩�H�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���E�����Ă���Ǘ�ł͎g�p���Ȃ� �@�s�o�Ƃo�b�u�ŒE���̕]���͉\�H�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���d�x�t�����ł́A��ɒE�����Ă��邽�ߓK���O �@�g�̌����̎��{ |
|||||||||||||||||||||||||
|
���̑��Ǝ��� |
����R�[�i�[�̃A�h���X�Fhttp://bivj.jp/QA/�@ID�Fbivj�@�p�X�F2014 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
�Z�~���g���̓l�R�Ɠ��ʂŃC�k�ł��g�p����Ă��Ă��� |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
�`�b�d�j�Q��Ƃ`�q�a�̕��p�͂��Ȃ��@������p�̑��� �@�����҂Ƃ��E�����ɂ͎g�p���Ȃ��@������p�������₷�� |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
�A�Ɍ��t���܂܂ꂽ�ꍇ�̂t�o�b�͂ǂ��]������̂��H �@�ʏ�t�o�b�͏㏸����@���a�����A�t�o�b���T���邱�Ƃ͂Ȃ����� �@���O�D�S��O�D�T�Ȃ�A���A�̎��Â��s���Ă���ĕ]������ |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
�s���x���^���g�p���ɏǏ�����A���ʂ��Ă��ǂ����H �@�O�D�Q�T�����^��������O�D�T�����^�����͂悭�s���Ă���B����ŕ���p�͌o�����Ă��Ȃ� �@�O�D�V�T�����^�����ł������ƌ����l������@�����̓_�͂킩��Ȃ� |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
���̂t�o�b�̉��߁A�L�̂悤�ɒႢ�Ƃ��납�玡�Â���̂��H �@��������������Ȃ� |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
�l�q�ł`�b�d�j�Q�܂���`�q�a�ɕύX����ۂɋC�����邱�Ƃ́H �@���E�����Ă���ꍇ�̓_���@���b�������T�ȏ�͒ʏ�E�����������Ă���ƍl���� �@�@���`�b�d�j�Q�܂Ƃ`�q�a�ł͂��̓_�ł͍��͂Ȃ� |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
�`�b�d�j�Q�܂͂b�������T����Ǝg��Ȃ��B�`�q�a���H �@���E�����Ă����������_���B�b�����T�ȏ�͒ʏ�E�����������Ă���ƍl���邽�߃_�� �@�@�`�b�d�j�Q�܂Ƃ`�q�a�ł͂��̓_�ɈႢ�͂Ȃ� |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
�V���f�i�t�B���̎g�����́H�a�h�c�H �@���r�h�c�ł͌����Ȃ��B�s�h�c�ł͔�p��������B |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
�L���H��ɂa�t�m�͏㏸����̂��H �@��������ƍl���� |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
���R�A�Ɛ��h�A�Ƃ̈Ⴂ�́H �@���t�o�b������̂Ȃ�ǂ���ł����܂�Ȃ� |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
�̔A���Ԃ́H �@���A��d�͒����A�V�`�W���Ԑ�H��ɑ���B�t�o�b�͎��ԂɈˑ����Ȃ��B |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
�E���̕]�����@�́H �@���畆�E�ݎ����B�����Ă���Ƃ킩��ɂ������ߌ������₷���B �@�@�����o���������Ă��Ȃ����Ō��Ă���B�b�q�s�i�э��Ǎď[�U���ԁj������Ƃ��ɓ����Ɍ��Ă���B |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
�N�b�V���O�ɑ��������x�������ǂɂ��āB�^�_���t�B���̌��ʂ́H �@�������炭�����ÏW�@���x�Ɍ����������邱�ƂŔx�������ǂɂȂ� �@�@������n��Ö@���A�ᕪ�q�w�p�����ȂǂŁA����Ɍ�������点�Ȃ����Â��s�� �@�@�@���v���s���O���������^���łP�^�S�����炢�ŁB �@�p���e�B���O�̈Ⴂ�@���N�b�V���O�̃p���e�B���O�͏��X�ɋN����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�x�����̃p���e�B���O�͓ˑR�N����B |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
�z�[���y�[�W��蔲�� |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
�V���f�B�i�t�B���̌��ʔ����܂ł̓����������Ă��������B �@���l�I�Ȉ�ۂƂ��Ă͔����͑��₩�ŁC���^���J�n���������`3���Ŏ��_�̕p�x�ɖ��炩�ȉ��P�������邱�Ƃ������ł��D |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
�S�s�S�̃R���g���[����������ɁA�A�����W�s����lj�����A���́A�s���x���_�����ʂ���A�ǂ�����s����ׂ��ł��傤���B �@��������͍��S�s�S�ł͂Ȃ��E�S�s�S�ł����?�@�ł���A���Âł͐Ö��g���Ɣx�������̒ቺ���|�C���g�ɂȂ�܂��B �A�����W�s���͏����ɖ��������g����ł��̂ŁA�E�S�s�S�ɂ͗L���łȂ��ƍl�����܂��B ����ɑ債�ăs���x���_���ɂ͔x�����g����p������̂ŁA�E�S�s�S�ł��L�v���Ǝv���܂��B �i�A���A�x�g���f�B���̓K�������͑m�X�ٕ��s�S�ǂł��j |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
�V���f�i�t�B��(�o�C�A�O��®)�͌��ł��l�ԓ��l�̕���p(�����u�N)�͂���̂ł��傤���H �܂��A���̕���p���A���^�ɂ����蒍�ӂ��ׂ��_�Ȃǂ�������Ă��������B �@�����������͂��̓_����ɖ������Y�ŐS�z���܂������A�u�N�����ɂȂ����Ǘ�͂���܂łɌo�����Ă��܂���B �܂��A�C�O�̕����ɂ����̂悤�ȗL�Q�����͋L�ڂ���Ă��܂���Bꋌa���̔畆�̔��Ԃ����ł͕���Ă��܂����A ���̂悤�Ȍo�������ɂ͂���܂���B |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
���̑m�X�ٕ��s�S�ǂɔ����P�ɑ��āA�ڕ��Ńu�g���t�@�m�[���̓������g�p���Ă����v�ł��傤���H ���̍ۂ̃u�g���t�@�m�[���̗p�ʥ�p�@�������ĉ������B �@��0.05�`0.1mg/kg�i�o��or�牺�j�Ŏg���Ă��܂��B�g�p�p�x��1��2�`4��Ƃ��Ă��܂��B �o���_�ɂȂ�܂����A0.5mg/kg���x�̃v���h�j�������P�ɗL���ȏꍇ������܂��B ���̂悤�ȏꍇ�A�S���a�ɂ�锭�P�ɉ����A�A�����M�[���C�ǎx���̗l�ȕa�Ԃ����P�ɊW���Ă����Ɛ�������܂� |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
�}�����S�s�S�Ŏg�p���鋭�S�܂͋�̓I�ɉ������g���ł����H �@����ړ����̋���������܂��͋�����ADB-cAMP�i�A�N�g�V���j�{�݂ł͎g���Ă��܂��B ���ɁA��ړ������ク��h�p�~�����g���A30���قǓ��^���ĔA�ʂ��������Ȃ���h�u�^�~����lj����Ă��܂��B |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
���S�s�S���y�x�ŁA�d�x�O��ًt���̂���E�S�s�S���ŁA�x�������ǂ��^���Ă��܂��B ���̂悤�ȁA�匴�������S�s�S�ł͂Ȃ��Ǝ��������x�������ǂ̏ꍇ�̓�����������Ē��������ł��B ���݂́A���������̂��߁AACEI�A�s���x���_���ALasix���g�p���Ă��܂��B �����Â͎�ɔx�������̒ቺ�i�x�����g����j����ѐÖ��g���ɂȂ�܂��B �o���_�ɂȂ�܂����A�x�������ɂ�镠���͗��A�܂ł͊Ǘ�������ȏꍇ�������A���̂悤�ȏǗ�ł͐��h�ɂ��z���őΉ����Ă��܂��B |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
ACEI�ɃA�����W�s���A�Ɏ_�C�\�\���r�h��lj����^����^�C�~���O�ɂ��ďڂ����������������B ���ʏ퉺�L�̗���ɂȂ�܂��B ACEI�ˊP�ˏɎ_�C�\�\���r�h�ˊP�˃s���x���_�� and/or �A�����W�s�� and/or ���A��(�x���) �A�����W�s���̓��j���A���W�I�e���V���n�����������Ă��܂��f�����b�g�����邱�Ƃ͒m���Ă����ׂ��ł��B |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
�L��BUN��40mg/dL�O��ACre��2-2.5mg/dL�A�A��d>1.035(�����p��d�v)�̏ǗႪ���܂��B���N�������悤�Ȑ��l�ł��B �ǂ̂悤�ɍl����Ηǂ��̂ł��傤���B �@�������A���Y������Ă��邱�Ƃ���A�A�Z�k�\�A�܂�A�Nj@�\�͐���ł�����̂́A Cre���������Ƃ��玅���̂�ߗʂ͒ቺ���Ă���ƍl�����܂��B �A��d��Cre�͑S���قȂ�t�@�\�����ꂼ��]�����Ă���ƍl���܂��B |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
ACEI���^���̏ǗႩ��Z�~���g���ւ̐�ւ��ɂ��ċ����ĉ������B ���x�[�����K�[���� ACEI���^���̏Ǘ�ŃZ�~���g���ɐ�ւ���ۂɂ́AACEI�̍�p���Ԃ��l����24-48���ԋĂ��������Ƃ����S�ł��B �܂��AACEI�̎�ނɂ���ẮA�L�ł̏��F��������܁i�L�ł̈��S���L�����̕]�����Ȃ���Ă��Ȃ��j������܂��̂ŁA ���̏ꍇ�ɂ�48���Ԉȏ�͊J���Ă����������������S�ł͂Ȃ����ƍl���܂��B |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
BUN�ACre�̏㏸�ɑ��ē_�H���Â��s�����A���ʂ𑝂₵�Ă��������Ȃ��ꍇ�A�L�Ƀh�p�~���̎����_�H�͌��ʂ���̂ł��傤���B �@���L�̐t���ɂ̓h�p�~����e�̂����Ȃ����Ƃ�����Ă��܂��B �܂��A�h�p�~���������̂�ߗʂ�{���ɏ㏸�����邩�ۂ����^�⎋����w�E������܂��B �����A�h�p�~���ɂ͋��S��p������܂��̂ŁA���S���ʂɂ��t�����ʂ��㏸���A ����ɂƂ��Ȃ��Ď����̂�ߗʂ��㏸����\���͂���Ǝv���܂��B |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
UPC�̐��m�ȑ�����@�́A�O�������ɏo���ȊO�ɉ@���ő���ł�����@����������Ă��������B �@���ꕔ�́A�@���p���t�����w�������u�ł͔A���`���A�A���N���A�`�j���̑��肪�\�Ȃ悤�ł��B �ڂ����͂��g�p�̌������u�̃��[�J�[�ɂ��₢���킹���������B |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
ACEI��UPC�̉��P�������Ȃ��ꍇ�ǂ����邩�B��̗ʂ𑝂₷�H��̎�ނ�ς���H �@��UPC�̃R���g���[���ɂ͐H���Ö@���d�v�ł��̂ŁA�����H���Ö@�����{���Ă��Ȃ��̂ł���A�܂��t���a�p�Ö@�H��lj����ĉ������B �܂��AACEI���J�n���Ă��S�g�������������P����Ȃ����UPC�͒ቺ���Ȃ����Ƃ������̂ŁA�����̃`�F�b�N���d�v�ł��B ACEI�݂̂ō��������R���g���[���ł��Ȃ��ꍇ�A���͌o���I��ACEI�ʂ����������ύX��������A �A�����W�s����lj������������ʓI���Ǝv���܂��i�Z�~�i�[�ł��b���������ƂƏd���ɂȂ苰�k�ł��j�B |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
���b���זE���g����CKD�̍Đ��Ö@�͖{���Ɍ��ʂ�����̂ł��傤���H �����̌�������1�Ⴞ�����ۂɔL���g���Ď����������Ƃ�����܂����A�����̂�ߗʂɑS���ω��͂���܂���ł����B 1�Ⴞ���ł����A���͗L�����͂��Ȃ�Ⴂ�̂ł͂Ƒz�����Ă��܂��B |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
�t���n���̏Ǘ�ŁA�G���X���|�G�`�����܂��g�����ǂ��������Y��ł��܂��B ��낵����A�ǂ�ȏǏ�A�^�C�~���O�Ŏg���n�߂�悢�̂������Ă��������܂���ł��傤���B �@���䂪���̑����̗Տ��b��t���uPCV��20%�����������l������v�ƍl���Ă���悤�ł����A���������ł��B �A���APCV�͐��a��Ԃɂ����E�����̂ŁA �{����PCV�������a��Ԃɂ��e������ɂ���Hb�Ŕ��f���ׂ����Ǝv���܂��i���ۂɐl�̈�Âł�Hb���d������Ă��܂��j�B ���錤���Őt���a�L��Hb��9(9�ȉ�)�A>9(9������)��2�Q�ɕ����Đ����\����r�����Ƃ���A���҂ɗL�Ӎ����o�܂����B �܂�AHb9�ȉ��̐t���a�L�͗\��s�ǂƂ������ƂȂ̂ŁA�n���ɉ������|�C���g�͂����ɂ���̂����m��܂���B |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
�Z�~���g���̓K���Ǘ�Ɣ��f�������_�Ōy�x�E�����F�߂��邱�Ƃ�����Ǝv���܂����A�����������̓����@�����������������B �@�����a�̈ێ��ɓw�߂Ȃ��瓊����J�n���A����Cre�l��0.4mg/dl���镝�ŏ㏸�����ꍇ�ɂ�GFR�̑傫�Ȓቺ������ƍl���A �x��������͌��ʂ��������܂��B �܂��A���ȏ��I�ɂ́A����J�n�O��Cre�l�Ɣ�r����30%�ȏ�̏㏸���p������ꍇ�ɂ͓������x�����������ƋL�ڂ���Ă��܂��B |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
�A���A���u�~��/�N���A�`�j����ɂ��āA���[�`���̑���Ƃ��Ă�UPC�ŏ\�����Ǝv���܂����A �A���A���u�~���𑪒肷��Ӌ`�ƃ^�C�~���O�ɂ��ċ����Ă��������Ȃ��ł��傤���B �@���������I�X�̂ŔA�ɐ��t�����������UPC�������ɏ㏸���܂��B �A���Ԓ��ɐ��q���m�F�ł��Ȃ��Ă����t��������������UPC�l�̌o��������܂��B �܂�A�������I�X�̂ł́AUAC�̑��肪�K�v��������܂���B |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
�L�̖����t���a�ɂ����āA������̓s���ɂ����{�p�x�����Ȃ��A���ʓI�ɂP��ʂ������Ȃ��Ă��܂��A�t�́A���ʓI�ł��傤���B �܂��A�����ɑ��镉�S(�댯)�́A�傫���ł��傤���B �@���牺�_�H�̗ʂɊւ��閾�m�ȃK�C�h���C���͂���܂���̂ŁA�̂̐��a��Ԃ����Ȃ�����{����Ηǂ��ł��B �����z���Ɉُ킪�Ȃ��̂ł���A1���̑��ʂōl���Ė�肠��܂���B ������̐S�؏ǂ��B��Ă��Ȃ���A��ʂł����Ă����S���Ǝv���܂��B
�A�t���܂̎�ނƂ��ẮA���_�����Q���ŏ\���ł��B 5%���t�́A�̓��ł͂����̐��Ƃ��ē����Ă��܂����߂Ɍ����Z�����ቺ�ɂ������ʌ����������邽�ߊ��߂��܂���B ����ɓ��t�͍ۂɂƂ��Ă͉h�{���ƂȂ邱�Ƃ���������ł��܂���B |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
ARB�̔L�̐S���a�ɑ��Ă̒m��������Βm�肽���ł��B �@���L�̍��S���g�D�ɂ����Ă�ACE�ł͂Ȃ��L�}�[�[������A���W�I�e���V���U�Y�����D�ʂɂȂ��Ă��邱�Ƃ�����Ă���A ���ۂ�ACEI�ɔ�ׂ�ARB�̕����S�ؐ��ۉ��}�����ʂ����������Ƃ��������܂��B
�����p���i�ɂ����āA�L�̐S���a�ւ̏��F������ACEI��ARB�͌��݂���܂���̂ŁA��������K���O�g�p�ɂȂ�܂��B �܂��AARB�̐S���a�ւ̎g�p�Ɋւ����p�ʂɂ��Ė��m�Ȓ�߂͂���܂���̂ŁA �b��t�̐搶�̂����f�ɂĂ��g�p�����������Ƃɂ͂Ȃ�܂��B |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
�V����MR�ǗႪ�x������N�����܂����B����܂�ACEI�������^���Ă��炸�A�t���Z�~�h�A�X�s���m���N�g���A�s���x���_���i0.25�r/kgBID�j���X�^�[�g���܂����B �t���Z�~�h1.5�r/kgBID��7���Ԃœ��^�����Ƃ���ABUN�����l�ƂȂ�A�t���Z�~�h���ʂ��Ă݂Ă��܂�BUN�����l�ł��B Xray��܂��x��������c���Ă��邽�߃t���Z�~�h0.7�r/kgBID�𑱂��Ă��܂��B�s���x���_��0.5�r/kg�ɑ��ʂ��ׂ��ł����H ����Ƃ������̔x����Ȃ�t���Z�~�h���ׂ��ł����H �@���y�x�Ƃ����ǂ��x����͓�����QOL����Q����̂ŁA���͂��Ƃ��y�x�ł����Ă��x����͖����������邱�Ƃɔ��ł��B �t���Z�~�h���^��ɍ����f���ǂ�������ꍇ�A�܂��\���Ȉ������A�h�o�C�X���A�S���a�p�Ö@�H���J�n���܂��B ����ɗ��A�܂ɂ��ẮA�t���Z�~�h�𒆎~���A���̂����ɃT�C�A�U�C�h�n���A�܂ƃX�s���m���N�g���̕��p�Ö@���J�n���܂��B �܂��A�s���x���_���𐄏��ʂ̔{�ł���0.5mg/kg BID�ɂ���Ɨǂ��Ǝv���܂��B |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
�j�g���[��(�Ɏ_�C�\�\���r�h)�����Âɗp���Ă��邩���������Ă������������B ���ׂ�{��l�ɂ���āA�Ɏ_�C�\�\���r�h�͗p����A�܂��͗p���Ȃ��ƈӌ����킩���̂ŁA�|���搶�̈ӌ����������������ł��B �@�����b��̏z��Ȃł́A�ʏ퉺�L�̗���Ŋe��܂��g�p���Ă��܂��B ACEI�ˊP�ˏɎ_�C�\�\���r�h�ˊP�˃s���x���_�� and/or �A�����W�s�� and/or ���A��(�x���) |
||||||||||||||||||||||||||
|
�Z�~���g���̏Љ� |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
�Z�~���g���F�S�����^�����A�o���t�A�L�p �q�`�`�n�}���܁F���j���A���W�I�e���V���A���h�X�e�����n�}���� |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
�����́A�e���~�T���^�� �q�g�ł́A�~�J���f�B�X |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
�p�ʁF�P�����^�����@���O�D�Q�T�����^���� |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
�����t���a�@���@�\���l�t�����̌����@����Ӑ����J�j�Y���F�c���l�t�����̕��S��@����ݱݼ�ݼݱ����n�̊����� �@�@�@�@�@�@���S�g���������@���ߏ�Ȍ��ǎ��k�ɂ�鎅���̍������ǁ@���`���A�@���l�t������Q�@������Ȃ�l�t�����̌��� |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
�`���A�́A�t���A�NJԎ����t�������������� |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
�A���W�I�e���V�m�[�Q�� �@�@�@�@�������j�� �A���W�I�e���V���T �@�@�@�@�����A���W�I�e���V���ϊ��y�f�@�@���`�b�d�j�Q��͂�����j�Q���� �A���W�I�e���V���U �@�@�@�@�� �`�s�P��e�́i�A���W�I�e���V���U�^�C�v�P��e�́j�@�A�`�s�Q��e�́i�A���W�I�e���V���U�^�C�v�Q��e�́j �@�@�@�@�� ���ǎ��k�A���ۉ��A�זE���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@���NJg���A���ۉ��}���A�זE���B�}���� ���Q�̎�e�̂̍�p�͝h�R���� |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
�`�b�d�j�Q�܂́A�`�s�P���`�s�Q�̗}�������B�܂��A�`�b�d�G�X�P�[�v�������A�A���W�I�e���V���Q���ʌo�H�ŎY�������B �`�q�a�́A�`�s�P�̂ݑI��I�ɑj�Q����B�܂��`�b�d�G�X�P�[�v�����̉e�����Ȃ� |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
�`�q�a�͂t�o�b�ቺ���V���ڂ܂łɒቺ�����̂ɑ��A�`�b�d�j�Q�܂́A�ቺ�����㌳�ɖ߂����@���`�b�d�G�X�P�[�v |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
����p �@�܂�ɚq�f�A��ցA���� �@�����ቺ�ɂ�鋕�E�A�ӂ�� |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
�K����̒��� �@�}���t�s�S�A�����̔A�ŏǂł͓��^������邱�� �@���E�����A�A�ŏǏǏ�ɘa�̂��߂̑ΏǗÖ@���D�悳���Ƃ��Ɏg�p���Ȃ� |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
���� �@�֒��r���A�Q�O�`�R�O���ōō������Z�x�A�������V�D�V���� �@�`�s�P��e�̂ւ̌������Ԃ͒����A��p�͂Q�S���ԕێ������ |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||